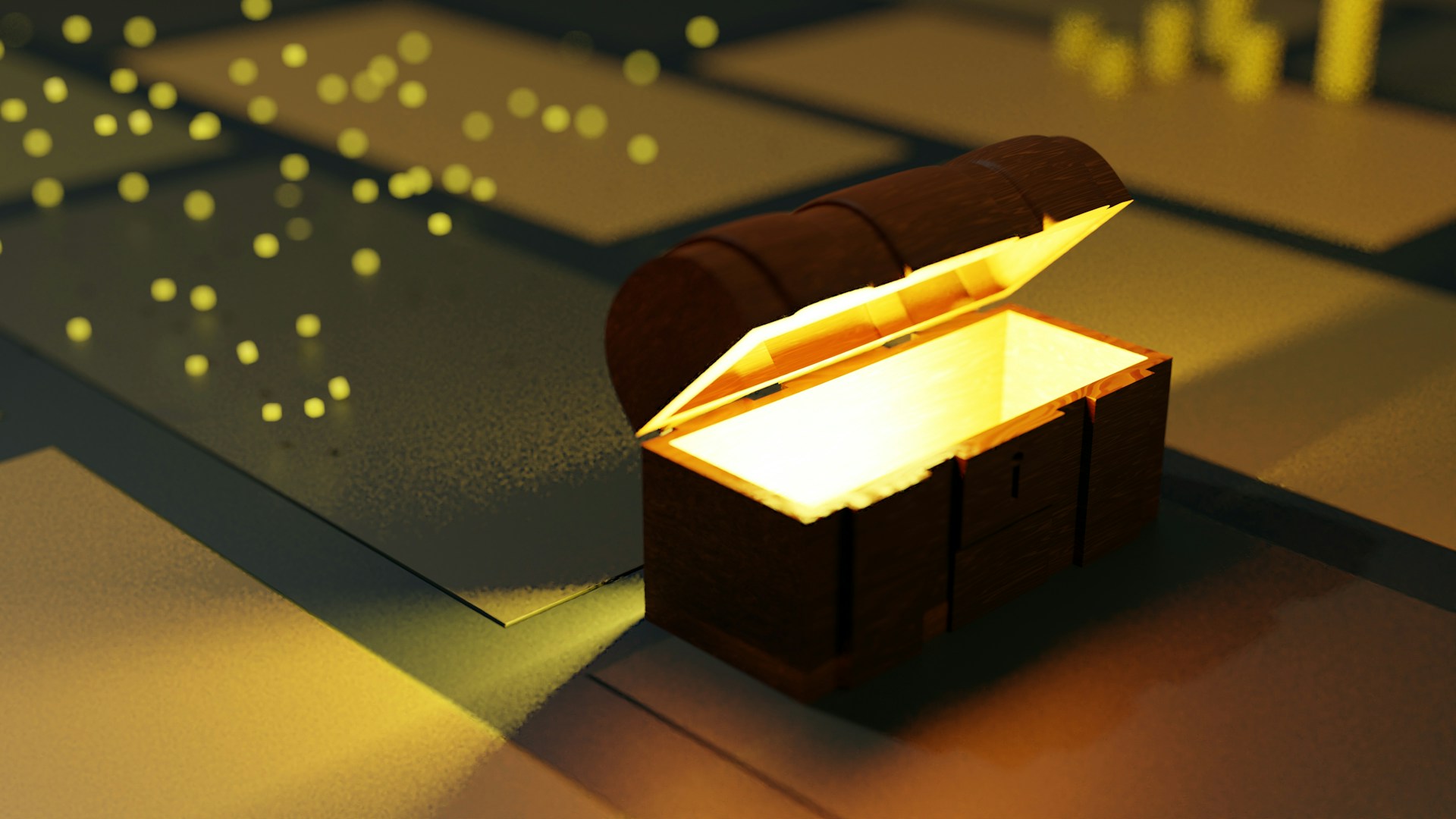
1868年、江戸幕府が政権を朝廷に返上した直後、官軍は江戸を目前に進軍。西郷隆盛と勝海舟の交渉により江戸無血開城が成立し、4月11日には江戸城が官軍の手に渡った。
城内の調査で多くの武器は見つかったものの、最も注目された幕府の金蔵には金銀が一切なかった。蔵番の役人25人を尋問しても誰一人情報を漏らさず、全員が処罰されたという。
その5日後、横浜港から「ブルガリア国旗」を掲げた1隻の蒸気船が上海へと出航。これが後に“幕府御用金400万両”を積んだ脱出船だったという説が浮上している。
このような背景の中で、かねてより注目される徳川埋蔵金伝説の中には、「赤城山」説以外にもいくつかの有力な埋蔵伝承が存在する。
数多く存在する埋蔵金伝説
埋蔵金伝説は日本各地に存在し、特に有名なものには以下の4例がある:
-
豊臣秀吉の埋蔵金(兵庫県)
晩年、息子・秀頼の将来を案じた秀吉は、4億5000万両と金塊3万貫を多田銀山に隠したとされる。巻物や図面も多く残されている。 -
武田信玄の埋蔵金(山梨県)
領内の金山で得た財宝を軍用道路沿いに隠させたとされ、これを示す書付を部下・穴山梅雪が持っていたと伝えられる。 -
明智光秀の埋蔵金(京都・滋賀)
本能寺の変後に手に入れた黄金の一部を、家臣の明智秀満が琵琶湖などに隠したとの言い伝えがある。 -
帰雲城の埋蔵金(岐阜県)
1586年の大地震による山崩れで城と共に埋没。最大2兆円相当の黄金が眠っているという説がある。
これらは未発見だが、近年の工事現場などで偶然に大量の金銀貨が見つかるケースもあり、完全なフィクションとは言い切れない。
徳川埋蔵金は存在するのか?
江戸幕府末期の財政難は事実だが、江戸城開城時に金蔵が空だったという点には不自然さが残る。少なくとも何らかの備蓄は存在した可能性が高いとされる。
その隠し場所として有力視されるのが「群馬県赤城山麓」である。勘定奉行だった小栗忠順が、自領であった赤城山周辺に御用金を移送したとする説が、メディアでもたびたび取り上げられてきた。
小栗はフランスと連携して横須賀製鉄所を設立した先進的な幕臣であり、官軍から警戒されていた人物であることも、この説の背景にある。
もう一つの有力説:「早丸」蒸気船の謎
もう一つ注目されるのが、仙台藩の蒸気船「早丸」に関する説だ。
全長46メートル、鋼鉄製のスクリュー船である「早丸」は、1868年4月16日(新暦5月8日)に横浜を出港。名目は上海との貿易だったが、実際には徳川御用金を密輸出する極秘任務だったとされている。
不可解なのは、「早丸」が仙台藩の船であるにもかかわらず、ブルガリア国旗を掲げて外国船を装い、多数の外国人船員を乗せていたこと。また、夜間に水先案内人なしで出港するという異例の行動も、秘密裡の任務を示唆している。
仙台藩と徳川家の密接な関係
当時、仙台藩は一時官軍側だったが、旧幕府側との対立を避け、後に奥羽越列藩同盟に参加して敗北。藩主・伊達慶邦の妻は徳川慶喜の妹であり、両者は義理の兄弟という親密な関係にあった。
江戸市内には仙台藩の複数の屋敷が存在し、特に芝口の上屋敷(現在の東新橋付近)は東京湾に直結する水運の要所。ここから御用金を横浜へと搬送した可能性が高い。
なお、同地では後の再開発時に石垣造りの船着き場が発掘されている。
蒸気船「早丸」から広がるもう一つの可能性
大型の蒸気船は江戸市中に直接乗り入れが困難であるため、江戸からの輸送には一般の荷船や漁船を偽装した方法が用いられた可能性が高い。これにより、「早丸」は横浜から密かに出航することができた。
徳川埋蔵金の伝説は今なお謎に包まれているが、「赤城山説」と「早丸説」の二本柱が、現代の歴史ロマンとして人々の関心を引きつけてやまない。真実が明らかになる日は訪れるのだろうか。
